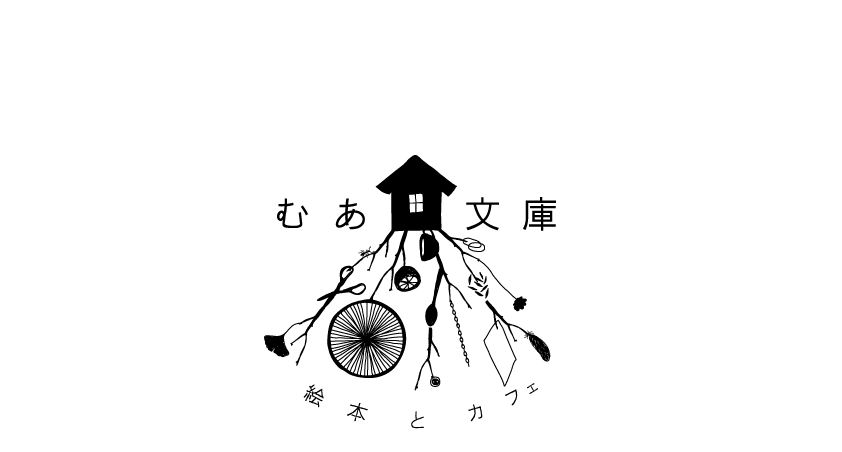2019/7/8
「びんのそら」
谷内六郎 詩/絵(至光社/1974年出版)
何かと何かが似ていると思うことはよくあります。ガラスびんの透き通った冷たい手触り、徐々に消えていく炭酸の泡、冷たく澄んだ夜の空気、朝になって消えていく星々、そうやって結びつくものごとたち。そんな結びつきを根拠のない非科学的な妄想だと片付けてしまうことは私にはできません。滑らかな陶器に触れるとき、ゴツゴツした木の幹に触るとき、焼けた砂漠の熱い砂に触れるとき、陶器、木、砂という言葉以上に私はその手触り、冷たさ温かさ、重さ軽さ、明るさ、鮮やかさ、大きさといったたくさんの情報を得ています。その情報を元に熱すぎて火傷しないか、重すぎて怪我しないか、明るすぎて目を傷めないか、自らの身体と相対化させながら身を守り、物を把握しているように思うのです。目から、皮膚から、全身で感覚を研ぎ澄ませて世界に無意識に開いている身体が受け取ったあらゆる情報の中で、頭の記憶にはなくても結びつくもの同士があってもけっして不思議ではないと思います。そもそもその物だけを純粋に見るということなどできるのでしょうか。目の前の丸い謎の物体を見ながら、それに似た小石、野球のボール、丸いドアノブ、水晶玉、その物の向こうにある何かを見ている、ふいに訪れるそんな世界の見え方が、そのまま一冊になったような、今は絶版となった1974年発行の絵本です。